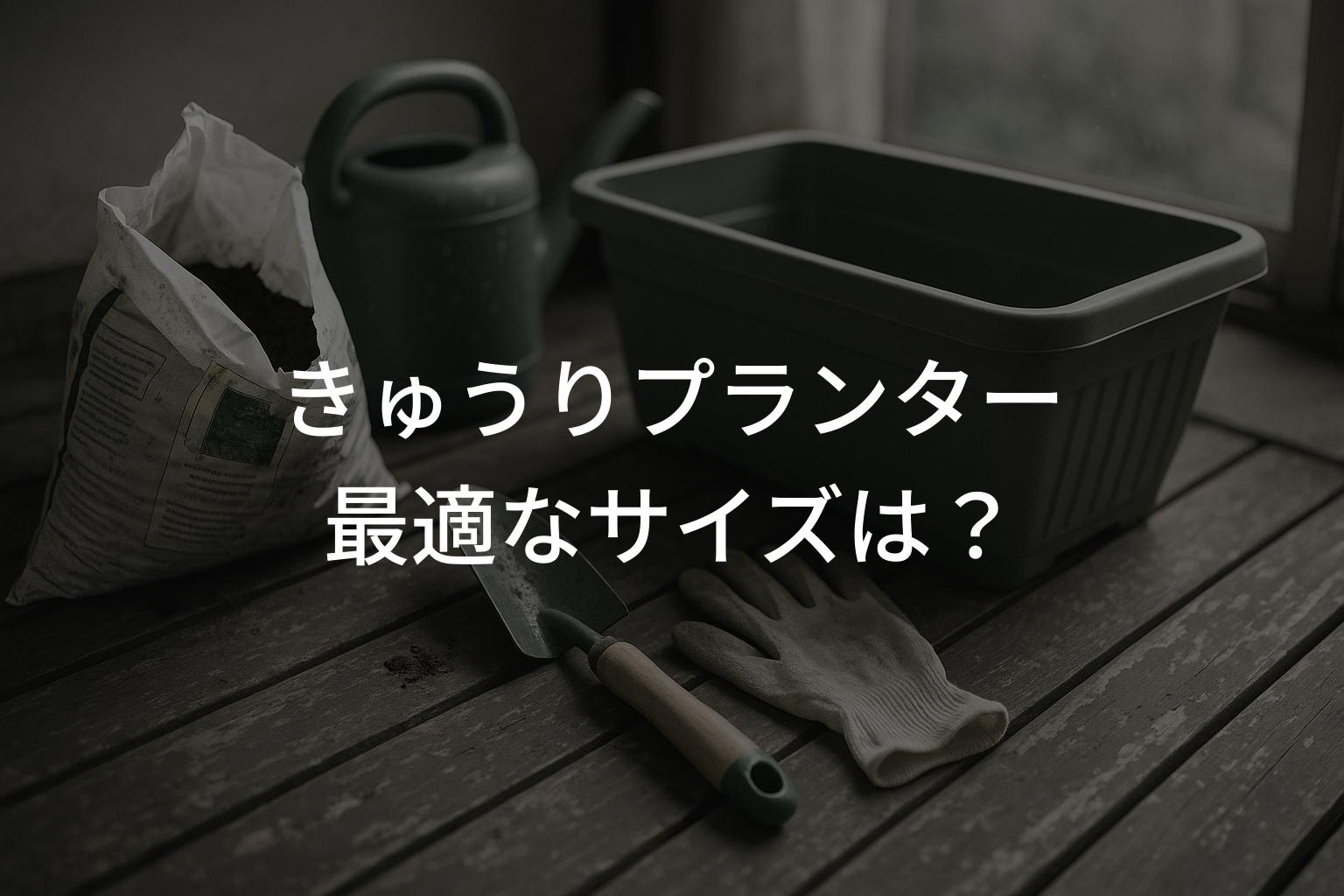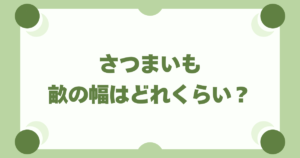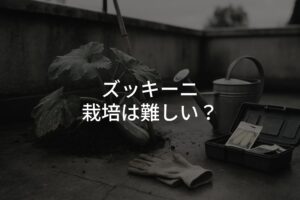家庭菜園できゅうりを育ててみたい!そう思って準備を始めたはいいものの、「きゅうりのプランターって、どのくらいのサイズを選べばいいんだろう?」と手が止まっていませんか?
ここ、気になりますよね。実は、プランターのサイズ選びは、きゅうり栽培の成功を左右するめちゃくちゃ大事なポイントなんです。
プランターが小さすぎると根っこが窮屈になって元気に育たないし、逆に大きすぎても管理が難しくなることがあるんですよ。
この記事では、きゅうり栽培に最適なプランターのサイズや深さ、必要な土の量(何リットルか)、そして1つのプランターに何株まで植えられるのか、といった初心者が抱える疑問に全部お答えしていきます。
ベランダでの省スペース栽培のコツや、具体的なおすすめ商品、支柱の立て方まで詳しく解説するので、ぜひ参考にしてくださいね!
- きゅうりに最適なプランターのサイズと深さ
- 必要な土の量や1プランターに植える株数
- 初心者におすすめのプランターの種類と特徴
- プランター栽培を成功させる育て方のコツ
きゅうりプランターのサイズ選びの基本

まずは、きゅうり栽培の土台となるプランター選びの基本から見ていきましょう。
サイズはもちろん、材質や形状によっても育てやすさが変わってくるので、それぞれの特徴を知っておくのが成功への近道ですよ。
プランターの深さは30cm以上が目安
きゅうりのプランター選びで、絶対に外せない最重要ポイント、それが「深さ」です。なぜそんなに大事かというと、プランターの深さが、きゅうりの生命線である「根」が快適に過ごせる環境を直接左右するからなんですよ。
きゅうりの根は、専門的には「浅根性(せんこんせい)」と呼ばれていて、地中深くまで伸びるというよりは、地表近くを広く浅く広がるタイプです。これだけ聞くと、「じゃあ浅いプランターでもいいんじゃない?」って思っちゃうかもしれないですよね。でも、そこがプランター栽培の落とし穴なんです。
なぜ「深さ」が水管理の鍵になるのか
プランター栽培は、地面で育てるのとは違って、土の量が限られています。特に真夏になると、浅いプランターは直射日光と高い気温ですぐに土がカラカラに乾いてしまいます。
きゅうりは体の90%以上が水分でできている野菜なので、水切れは致命的。深さのあるプランターは、それだけ多くの土を保持できるため、保水力が高まります。これが、夏の厳しい乾燥からきゅうりを守るための、いわば「貯水タンク」の役割を果たしてくれるわけです。
理想を言えば、深さは30cm以上を確保したいところ。最低でも25cmは欲しいですね。スコップがすっぽり入るくらいの深さとイメージすると分かりやすいかもしれません。この深さがあれば、根が伸びるスペースを確保しつつ、土全体の水分量が安定し、水やりの手間も少し楽になりますよ。
浅いプランターが招く3つのリスク
- 水切れ地獄:夏場は朝夕2回の水やりでも追いつかないほど乾燥しやすく、ちょっと油断するとすぐに葉がしおれてしまいます。
- 根の高温障害:コンクリートの照り返しなどでプランター内の温度が上昇し、根がダメージを受けて成長が止まってしまうことがあります。
- 株の不安定化:きゅうりは上にどんどん伸びていくので、浅いプランターだと株が不安定になり、強い風で倒れやすくなります。
深さと一緒に、幅(長さ)も重要です。きゅうりの根は横にも広がるので、深さだけあっても幅が狭いと、根が窮屈になってしまいます。「幅広で適度に深い」というのが、きゅうりプランター選びのキーワードだと覚えておいてくださいね。
必要な土の量とリットルの目安
最適な深さのプランターを選んだら、次に考えたいのが「どれくらいの土を用意すればいいの?」という点。これもすごく大事なポイントで、土の量がきゅうりの生育に直結します。
結論から言うと、きゅうり1株を健康に育てるために必要な土の量は、最低でも10リットル、できれば15リットル以上が目安になります。これは、きゅうりが成長するために必要な水分や養分を蓄えておくための、最低限の量だと考えてください。
プランターサイズと土容量の関係
プランターの容量は「L(リットル)」で表記されていることが多いので、購入時にチェックする習慣をつけるといいですよ。市販のプランターで、どのサイズがどれくらいの容量なのか、ざっくりとした目安を表にまとめてみました。
| プランターの種類 | 一般的なサイズ | 土容量の目安 | 育てられる株数 |
|---|---|---|---|
| 丸型鉢(深鉢) | 10号(直径約30cm) | 約12L | 1株 |
| 標準プランター | 幅 約50cm | 約15L~20L | 1株 |
| 大型プランター | 幅 約65cm | 約25L~40L | 1~2株 |
※上記はあくまで目安です。製品によって深さや形状が異なるため、実際の容量は商品表示で確認してくださいね。
土の量をケチるとどうなる?
「ちょっとくらい少なくても大丈夫でしょ?」と思って土の量をケチってしまうと、後々いろんなトラブルが出てきやすくなります。
- 肥料切れ・水切れ:土が少ないと、蓄えられる養分も水分も少ないため、すぐに不足してしまいます。結果、葉の色が薄くなったり、実の付きが悪くなったりします。
- 根詰まり:限られたスペースで根がぎゅうぎゅう詰めになり、うまく水分や養分を吸収できなくなります。
- 生育不良:全体的に株が大きくならず、ひょろひょろとした弱々しい育ち方になってしまいます。
市販の「野菜用培養土」は、20Lや25Lといった容量で販売されていることが多いです。1株育てるなら20L袋を1つ、幅65cmのプランターで2株育てるなら25L袋を2つ用意しておくと、余裕をもって準備できるかなと思います。土を入れる際は、プランターの縁から3〜5cmほど下までにして、水やりのための「ウォータースペース」を確保するのを忘れないでくださいね。
1つのプランターに何株植えられる?
プランターの準備ができると、「せっかくだからたくさん植えて、いっぱい収穫したい!」という気持ちが湧いてきますよね。私も最初の頃はそうでした。でも、きゅうりのプランター栽培では、この「植えすぎ」が失敗の大きな原因になるんです。
一般的な幅65cm程度の大型プランターを使う場合でも、植え付けは最大で2株までにしてください。そして、もしあなたが家庭菜園初心者なら、まずは「1つのプランターに1株」で挑戦することを強くおすすめします。
なぜ「植えすぎ」はダメなのか?
理由は、植物たちの間で壮絶な「生存競争」が起きてしまうからです。この競争は、目に見えない土の中と、目に見える地上部の両方で発生します。
1. 根の競合(水と養分の奪い合い)
プランターの中の土の量は限られています。そこに複数の株を植えると、それぞれの根が水分や養分を求めて伸びていき、やがてお互いの根が絡み合ってしまいます。こうなると、限られたリソースを株同士で奪い合うことになり、生育に差が出たり、最悪の場合は全ての株が栄養不足で弱ってしまう「共倒れ」状態に陥ることもあります。
2. 地上部の競合(日照と風通しの悪化)
きゅうりの葉は結構大きくなります。株間が狭いと、成長するにつれて葉が重なり合い、下の葉に日光が当たらなくなります。光合成ができない葉は役目を果たせず、病気の原因になることも。さらに、葉が密集すると風通しが悪くなり、湿気がこもりやすくなります。これは、きゅうりの大敵である「うどんこ病」などのカビ系の病気が発生する絶好の環境を作ってしまうんです。(出典:タキイ種苗株式会社「きゅうりの病害虫」)
収穫量を増やすコツは「株間」にあり!
実は、無理に密植するよりも、1株を大切に育てた方が、結果的にたくさんのきゅうりを収穫できることが多いんですよ。1株に十分なスペースと栄養を与えることで、株が健全に大きく育ち、次から次へと実をつけてくれます。もし2株植える場合は、必ず株と株の間(株間)を最低でも30cm、できれば40cmは確保して、お互いがのびのび育てる環境を作ってあげてくださいね。
初心者におすすめの市販プランター3選
「理屈は分かったけど、じゃあ具体的にどれを買えばいいの?」と思いますよね。そこで、全国のホームセンターや園芸店、オンラインストアで比較的手に入りやすい、きゅうり栽培にぴったりの定番プランターを3つピックアップしてみました。
「これはいいな!」と感じたものばかりなので、ぜひ選ぶ際の参考にしてみてください。
1. アイリスオーヤマ「菜園プランター」シリーズ
まず、初心者さんが最初に手に取るプランターとして間違いないのが、このアイリスオーヤマのシリーズです。特に「深型65」といった、幅65cmで深さが30cm以上あるモデルは、きゅうり栽培の条件にぴったり。土もたっぷり40L前後入る製品が多く、2株植えにも対応できます。私が特に気に入っているのは、プランターの側面に支柱を差し込んで固定できるホール(穴)が付いている点です。これがあると、支柱がグラつくのを防ぎ、ネットを張る作業が格段に楽になります。底面もメッシュ構造になっているものが多く、排水性と通気性への配慮もバッチリ。価格も手頃で、まさに「初心者のための王道プランター」と言えるでしょう。
2. リッチェル「深型野菜プランター 65型」
こちらも園芸用品メーカーとして非常に信頼性の高いリッチェル社の製品です。アイリスオーヤマ製と同様に、幅65cmの深型がラインナップされています。リッチェルのプランターは、プラスチックが肉厚で、作りが非常にしっかりしているのが特徴。長く使いたいという方には特におすすめです。デザインも落ち着いたグリーンやアイボリー系のものが多く、ベランダの雰囲気を壊しません。製品によっては、底にスノコ状のパーツが付属しており、鉢底石を使わなくても根が直接水に浸かるのを防ぎ、通気性を確保してくれる工夫がされています。こうした細やかな配慮が、さすが老舗メーカーだなと感じさせますね。
3. アップルウェアー「野菜鉢33型(深鉢)」
「ベランダが狭いから、大きな長方形プランターはちょっと…」という方や、「まずは1株だけお試しで育ててみたい」という方には、この丸型の深鉢が最適です。直径33cm、高さ27cmと、省スペースながら1株育てるのに必要な土容量(約14L)をしっかり確保できます。このプランターの最大のメリットは、寸胴(ずんどう)形状で安定感があり、倒れにくいこと。きゅうりは成長すると背が高くなるので、安定感はとても重要です。厚手で丈夫なプラスチック製で、底面に脚がついているため、地面からの熱や湿気を防ぎ、通気性を確保してくれます。ベランダの隅っこでも、立派なきゅうりを育てられますよ。
ちょっと上級者向け?「底面給水式プランター」
「毎日の水やりが大変そう…」と不安な方には、プランターの底に貯水スペースがある「底面給水式」という選択肢もあります。貯めておいた水を自動で吸い上げてくれるので、水やりの頻度を減らせるのが最大のメリット。ただし、長雨の時期に水が溜まりすぎて根腐れの原因になることもあるので、排水栓の管理など、少しコツが必要です。
プラスチックと素焼きのメリット
プランターのサイズや形と並んで、意外と栽培のしやすさを左右するのが「材質」です。家庭菜園でよく使われるのは、主に「プラスチック製」と「素焼き(テラコッタ)製」の2種類。それぞれの特性を理解して、あなたの栽培環境に合ったものを選びましょう。
プラスチック製プランター:初心者向けの万能選手
今や家庭菜園の主流となっているのが、ポリプロピレンなどを原料とするプラスチック製のプランターです。私もほとんどの野菜をプラスチック製で育てています。
メリット
- 軽くて扱いやすい:土を入れても女性一人で楽に持ち運べるので、日当たりの良い場所に移動させたり、台風の時に避難させたりするのが簡単です。
- 価格が手頃:素焼きに比べて安価な製品が多く、気軽に始めやすいのが魅力です。
- 保湿性が高い:材質が水を通さないため、土が乾きにくいです。これは水をたくさん必要とするきゅうりにとって大きなメリットになります。
- 機能的で種類が豊富:支柱ホルダー付きやスリット入りなど、野菜栽培に特化した便利な機能を持つ製品がたくさんあります。
デメリットと対策
一方で、注意点もあります。最大のデメリットは通気性の低さです。土が常にジメジメしていると、根に酸素が届かず「根腐れ」の原因になります。これを防ぐために、必ず鉢底石をしっかり敷いて、水はけを良くする工夫をしてください。また、夏場は直射日光で鉢が高温になりやすいので、白など明るい色のプランターを選んだり、すのこ等の上に置いたりして対策すると良いでしょう。
素焼き(テラコッタ)製プランター:呼吸する植木鉢
粘土を焼いて作られた素焼きの鉢は、ナチュラルでおしゃれな見た目が人気ですよね。見た目だけでなく、植物の生育にとっても素晴らしい特性を持っています。
メリット
- 通気性・排水性が抜群:鉢の表面には目に見えない無数の穴が開いていて、そこから空気や水分が出入りします。まさに「呼吸する鉢」で、根腐れのリスクを大幅に減らしてくれます。
- 夏場に涼しい:水分が鉢の表面から蒸発する際の気化熱で、鉢内の温度が上がりにくく、根を熱から守ってくれます。
デメリットと対策
最大の注意点は、土が非常に乾きやすいこと。特にきゅうりのように水を好む野菜を育てる場合は、夏場は朝夕2回の水やりが必須になることも。乾燥対策として、土の表面をワラなどで覆う「マルチング」を必ず行いましょう。また、大型のものは非常に重く、一度設置すると移動が大変です。落とすと割れてしまうのもデメリットですね。価格もプラスチック製より高価な傾向があります。
結論:初心者さんはまずプラスチック製から!
総合的に考えると、やはり初心者さんには、管理がしやすく機能的なプラスチック製の野菜用プランターがおすすめです。
栽培に慣れてきて、水やりの管理に自信がついたら、デザイン性の高い素焼き鉢にチャレンジしてみる、というステップが良いかもしれませんね。
ベランダ栽培での省スペースの工夫
「うちのベランダは狭いから、きゅうりなんて無理かな…」なんて思っていませんか?大丈夫です!きゅうりはツルを伸ばして成長する特性を活かせば、狭いスペースでも驚くほどたくさん収穫できるんですよ。そのためのキーワードが「立体栽培」です。
縦の空間を最大限に活用する「立体栽培」
立体栽培は、その名の通り、きゅうりのツルを上へ上へと誘引して、縦方向に育てる方法です。これにはたくさんのメリットがあります。
- 省スペース:横への広がりを抑えるので、プランターを置くわずかなスペースさえあれば栽培可能です。
- 日当たり・風通しの確保:葉が重なりにくくなるため、株全体にしっかり日光が当たり、光合成が活発になります。また、風通しが良くなることで、病気の予防にも繋がります。
- 収穫作業が楽:実がぶら下がる形になるので、見つけやすく、収穫も簡単です。まっすぐで形の良いきゅうりができやすいというメリットもあります。
やり方は簡単で、プランターの近くに長さ1.8m〜2m程度の支柱を立て、そこに園芸用のネットを張るだけ。ベランダの手すりや壁面を利用してネットを固定すれば、きゅうりの葉が日差しを遮ってくれる「緑のカーテン」にもなり、室内の温度上昇を抑える省エネ効果も期待できますよ。
プランターの設置場所と安全対策
ベランダで栽培する場合、プランターを置く場所にも少し工夫が必要です。まずは日当たりの確保。きゅうりは日光が大好きなので、できるだけ長時間、日の当たる場所に置いてあげましょう。
ちょっとした置き場所の工夫
もし日当たりの良い床面スペースがなければ、エアコンの室外機の上に専用のラックを設置して、その上にプランターを置くという方法もあります。こうすることで、高さが出て日当たりが改善されることがありますよ。ただし、製品の耐荷重は必ず確認してくださいね。
そして、集合住宅のベランダで特に気をつけたいのが、安全面と近隣への配慮です。
ベランダ菜園での重要注意事項
- 転倒・落下防止:きゅうりが成長すると、想像以上に重くなり、風の抵抗も受けやすくなります。支柱やネットは、手すりなどにしっかりと固定し、台風の時などは一時的に室内に取り込むなどの対策をしましょう。
- 排水への配慮:水やりをした際の水が、階下へ流れていかないように、必ずプランターの下に大きめの受け皿を敷いてください。
- 避難経路の確保:ベランダは火災時などの避難経路にもなっています。プランターや支柱で、避難ハッチや隣戸との隔て板を塞いでしまわないよう、配置には十分注意してください。
これらの点に気をつければ、限られたスペースでも安全に楽しくきゅうり栽培ができますよ。
きゅうりプランターのサイズに合う栽培のコツ

最適なプランターが用意できたら、いよいよ栽培スタートです!ここからは、選んだプランターのサイズを活かして、きゅうりを元気に育てるための具体的なコツを、さらに深掘りしてお伝えしますね。土作りから支柱の立て方、日々の管理まで、ちょっとしたポイントを押さえるだけで、収穫量がグンと変わってきますよ。
支柱の立て方と適切な高さ
きゅうり栽培のハイライトの一つとも言えるのが、支柱立てとネット張りです。これがうまくできると、見た目もきれいですし、その後の管理が驚くほど楽になります。逆に、タイミングが遅れたり、立て方が中途半端だったりすると、ツルが地面を這ってしまったり、風で倒れたりして大変なことになります。
支柱を立てるベストタイミング
支柱を立てるベストなタイミングは、苗を植え付けてから1〜2週間後、本葉が5〜6枚に増え、ツルが伸び始める直前です。早すぎると苗が小さくて作業しにくいですし、遅すぎると、すでに伸び始めたツルを傷つけてしまう可能性があります。「そろそろツルが伸びそうだな」と感じたら、すぐに設置作業に取り掛かりましょう。
プランター栽培におすすめの支柱の組み方
プランター栽培では、安定感があって、ツルが絡みやすい形に組むことが重要です。いくつか代表的な組み方を紹介しますね。
- 合掌(がっしょう)式:プランターの両端に1本ずつ支柱を斜めに差し込み、上部で交差させて結束する方法です。シンプルで安定感があり、1〜2株の栽培に向いています。交差させた部分に横に1本支柱(水平支柱)を渡すと、さらに強度がアップします。
- あんどん式:3〜4本の支柱をプランターの縁に沿って垂直に立て、数カ所をビニールタイや紐で輪っか状に固定していく方法です。ツルが自然に巻き付きやすく、コンパクトにまとまります。
- ネット利用型:合掌式や、プランターの四隅に支柱を立てて枠を作る「やぐら式」を組み、そこにきゅうり用のネットを張る方法です。これが最も管理しやすく、収穫量も期待できるので、私の一番のおすすめです。
どの組み方でも、支柱の高さは地上部で1.8m(180cm)程度になるようにしましょう。きゅうりのツルは放っておくと2m以上に伸びるので、これくらいの高さは必要です。支柱をプランターに差し込む際は、根を傷つけないように、株元から少し離れた場所に、できるだけ深く、ぐらつかないようにしっかりと差し込んでください。
ツルの誘引(ゆういん)のコツ
支柱とネットを設置したら、伸びてきたツルをネットに導いてあげる「誘引」という作業が必要になります。最初のうちは、ツルが自分で絡みつくのが下手なので、手伝ってあげるイメージです。麻ひもなどを使い、ツルの茎と支柱(またはネット)を「8の字」になるようにゆったりと結びます。きつく結びすぎると、茎が太くなった時に食い込んでしまうので、余裕を持たせるのがポイント。その後は、2〜3日に1回くらい様子を見て、伸びたツルをネットに絡ませてあげましょう。
水やりの頻度と量のポイント
きゅうり栽培の成否は「水やりで決まる」と言っても過言ではありません。特に、土の量が限られ、乾燥しやすいプランター栽培では、毎日の水やりが欠かせない日課になります。でも、ただやみくもに水をあげればいいというわけでもないんですよ。
水やりの基本リズム「乾いたら、たっぷり」
水やりの一番の基本は、「土の表面が乾いたのを確認してから、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与える」ことです。これを「乾湿のメリハリ」と呼びます。常に土がジメジメしていると、根が酸素不足になって根腐れを起こしてしまいます。一度たっぷり水をあげたら、次に土の表面が白っぽく乾くまで待つ。このリズムが、健康な根を育てる秘訣です。
時間帯別・水やりのポイント
- ベストな時間帯(朝):水やりは、気温が上がり始める前の涼しい朝に行うのが基本です。日中の活動に備えて、きゅうりが水分をしっかり吸収できます。
- 真夏の追加タイム(夕方):夏場、日中に葉がぐったりして、夕方になっても土が乾いているようなら、気温が下がってきた夕方にもう一度水やりをします。ただし、夜間に葉や土が濡れすぎていると病気の原因になるので、与えすぎには注意です。
- 避けるべき時間帯(昼間):炎天下の日中に水やりをすると、水滴がレンズ代わりになって葉が焼けたり、土の中の水分が熱湯のようになって根を傷める原因になるので避けましょう。
生育ステージで変わる水の必要量
きゅうりが必要とする水の量は、成長段階によって変化します。特に、実がなり始めてから収穫が続く時期は、人生(きゅうり生?)で最も水を必要とするタイミングです。この時期に水切れを起こすと、実が大きくならなかったり、苦味が出たり、曲がってしまったりと、品質に直接影響が出ます。実がどんどん大きくなり始めたら、いつもより少し多めに、そして乾燥具合をこまめにチェックしてあげてください。
忙しくて毎日の水やりが難しいという方は、ペットボトルを使った簡易的な自動給水器を作ったり、前述した底面給水プランターを利用したりするのも良い方法ですよ。
根が喜ぶ用土と排水対策
美味しいきゅうりを育てるためには、その土台となる「土」がふかふかで、栄養満点である必要があります。きゅうりの根は、水分だけでなくたくさんの酸素も必要とするので、「水はけ」と「水持ち」という、一見矛盾するような性質を両立させた土が理想的なんです。
初心者さんは「野菜用培養土」一択でOK!
土作りは奥が深くて、赤玉土や腐葉土などを自分でブレンドする方法もありますが、初心者さんは迷わず市販の「野菜用培養土」を使いましょう。これには、きゅうりの生育に必要な元肥(もとごえ)と呼ばれる初期肥料や、土の水はけを良くするパーライトなどが、あらかじめ絶妙なバランスで配合されています。袋を開けてそのままプランターに入れるだけなので、本当に手軽で失敗がありません。
ワンランク上を目指す「ちょい足し」テクニック
もし、さらに良い土を目指したいなら、培養土に一工夫加えるのもおすすめです。
- 排水性を高めたい場合:「パーライト」や「軽石(小粒)」を全体の1割ほど混ぜ込むと、土の中に隙間ができて空気の通り道が増え、水はけがさらに良くなります。
ただし、やりすぎは禁物。基本は培養土をそのまま使い、もし「うちのベランダは乾燥しすぎるな」とか「ちょっと過湿気味かも」と感じたら、次回の植え付けの際に試してみる、というくらいで良いと思います。
絶対に忘れちゃいけない「排水対策」
どんなに良い土を使っても、プランターの底の水はけが悪ければ意味がありません。植え付け前のひと手間が、根腐れを防ぎ、きゅうりの健康を守ります。
植え付け前の3ステップ
- 鉢底ネットを敷く:まず、プランターの底にある排水穴の上に「鉢底ネット」を置きます。これは、水やりで土が流れ出てしまうのを防ぐためです。
- 鉢底石を入れる:次に、ネットが隠れるくらいまで「鉢底石」を敷き詰めます。厚さにして2〜3cmが目安。これにより、プランターの底に空間が生まれ、余分な水がスムーズに排出されます。
- 土を入れる:鉢底石の上から、用意した培養土をウォータースペース(縁から3〜5cm下)まで入れれば準備完了です。
鉢底石は軽石タイプのものを使うと、プランター全体の重量を軽くできるのでおすすめですよ。このひと手間を惜しまないことが、プランター栽培成功への大きな一歩になります。
複数株植えるときの株間
幅の広いプランターを使って、2株以上のきゅうりを育てることに挑戦する場合、最も重要になるのが「株間(かぶま)」、つまり株と株の間の距離です。この距離が、それぞれの株が健全に育つための生命線になると言っても過言ではありません。
なぜ「株間」がそんなに大事なのか?
「1つのプランターに何株植えられる?」のセクションでも触れましたが、株間が狭いと、日当たりや風通しが悪くなるだけでなく、土の中の限られた水分や養分を株同士で奪い合うことになります。その結果、
- 株全体の成長が遅れる
- 葉や茎が細く、ひょろひょろになる
- 病害虫が発生しやすくなる
- 収穫できる実の数が減ったり、小さくなったりする
といった、様々なデメリットが生じます。欲張って密植した結果、かえって収穫量が減ってしまった…なんてことは、家庭菜園でよくある失敗の一つなんです。
理想的な株間は「40cm」
きゅうりの場合、プランターで2株植えるなら、最低でも30cm、理想を言えば40cm以上の株間を確保してください。幅65cmのプランターなら、両端から12〜13cmくらい内側に1株ずつ植えれば、ちょうど40cmくらいの株間が取れる計算になります。
植え付けたばかりの頃は、苗が小さくてスカスカに見えるので、「もっと詰めても大丈夫そう…」と感じるかもしれません。でも、きゅうりの成長は驚くほど早く、1ヶ月もすれば葉が生い茂り、あっという間にスペースが埋め尽くされます。未来の姿を想像して、ぐっとこらえて、ゆったりと植え付けてあげましょう。
2株植えの際の支柱の立て方
2株植える場合は、それぞれの株の近くに支柱を立ててあげます。例えば、プランターの両端にそれぞれ支柱を立て、ツルを外側に誘引していくと、中央の空間が空いて風通しが良くなります。また、四隅に支柱を立ててネットを張る場合も、それぞれのツルが絡み合わないように、こまめに誘引して整理してあげることが大切です。
健全な株を育てるためには、ライバルを減らして、1株あたりのリソース(光・水・栄養・スペース)を最大限に確保してあげること。この考え方が、プランター栽培での収穫量アップに繋がります。
まとめ:最適なきゅうりプランターのサイズで成功
さて、ここまで きゅうりのプランター栽培について、サイズ選びの基本から、材質の違い、具体的な栽培のコツまで、かなり詳しく解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。たくさんの情報があって少し頭がパンクしそうになったかもしれませんが、大切なポイントは実はとてもシンプルです。
成功への3つの黄金ルール
最後に、これだけは絶対に覚えておいてほしい、きゅうりプランター栽培成功のための3つの黄金ルールをまとめます。
- プランターは「幅広・深型」を選ぶべし!
深さは最低でも25cm、できれば30cm以上。幅もゆとりのあるものを選びましょう。これが、夏の水切れや根詰まりを防ぎ、きゅうりがのびのび育つお家になります。 - 土は「1株15L」を目安にケチらない!
土はきゅうりのベッドであり、ご飯です。1株あたり15L前後の土量を確保してあげることで、栄養不足になることなく、元気に成長してくれます。 - 植え付けは「1プランター1株」から始めるべし!
特に初心者さんは、欲張らずに1株を大切に育てることから始めましょう。その方が管理が楽で失敗が少なく、結果的にたくさんの美味しいきゅうりに出会えます。
この3つのポイントを押さえて、あなたに合った最適なきゅうり プランターのサイズを選び、丁寧にお世話をしてあげれば、きっと家庭菜園の楽しさと、自分で育てた野菜を収穫する感動を味わえるはずです。
プランターと土と苗、そしてほんの少しの愛情があれば、あなたの家のベランダが、最高の「マイきゅうり畑」に変わります。この記事が、あなたのきゅうり栽培チャレンジの、成功への第一歩となれば、これ以上嬉しいことはありません。ぜひ、採れたてのみずみずしいきゅうりを味わってみてください!